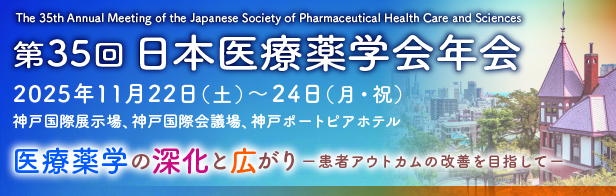日程表・プログラム
理事長講演
日本医薬品安全性学会の未来に向けて-これまでの発展と今後の展望-
8月2日(土)10:05~10:35 第1会場
座長 今給黎 修 福岡大学 薬学部 病院薬学教室 / 福岡大学筑紫病院 薬剤部
演者 佐藤 光利 一般社団法人日本医薬品安全性学会 理事長
シンポジウム1
8月2日(土)10:40~12:10 第2会場
9月30日を医薬品安全性の記念日にしよう!-身近な医薬品から患者を守るには-
国際薬剤疫学会代表を務めたJerry Avorn氏は2006年のN.E.J.Med誌で「9月30日を医薬品安全の不名誉の日に」と訴えた。2004年のこの日に、ロフェコキシブが心筋梗塞や脳卒中のリスクを2倍に高めたことを理由に回収された。この事件はICE-E2Eなど世界中の市販後臨床のあり方を見直すきっかけとなったが、日本ではどうだろうか。日本でも繁用されているNSAIDs、帯状疱疹に対する抗ウイルス薬療法、長期間の服用が必要なSGLT2阻害薬に焦点を当て、このような身近な医薬品から患者を守るためには、オール薬剤師で投薬の前から切れ目なく安全確保や副作用回避を図る必要があり、その重要性について理解を深めたい。
オーガナイザー 髙栁 和伸 倉敷中央病院薬剤本部 座長 髙栁 和伸 倉敷中央病院薬剤本部 月岡 良太 株式会社アインホールディングス 医療連携学術部
SY1-1 "売って終わり”にしないセルフメディケーション(OTC医薬品)
~薬剤師が関わる服薬後フォローの可能性~
松浦 克彦 愛知学院大学・薬学部 医療薬学科・医療薬学講座
SY1-2 アシクロビル脳症の予防・早期発見のために薬剤師ができること -院内での血中濃度測定の有用性-
松田 翔平 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 薬剤部
SY1-3 SGLT2阻害薬によるinitial dip誘発に関連するリスク因子の考察と臨床で着目すべきポイント
持田 知志 新潟医療生活協同組合 木戸病院 薬剤部
シンポジウム2
8月2日(土)10:40~12:10 第3会場
感染症治療薬の安全対策 -症例から見えてきた問題点への対応-
本シンポジウムの目的は、感染症治療薬の安全管理の問題点を探索・分析し、具体的な対応策の提言にある。感染症治療薬の安全性の問題点は、重大副作用、アレルギー、薬物相互作用、特殊病態下での薬物動態の変化、妊婦や授乳婦の使用制限、長期使用、耐性菌の出現など多岐にわたる。それ故、抗微生物化学療法には、多面的な安全管理が求められる。本シンポジウムでは、感染症治療薬による症例を提示し、安全上の問題点と対応について考察する。さらに、抗微生物薬の供給不足下での適切な薬剤選択についても議論する。本シンポジウムは、感染症治療薬安全対策部会が企画した最初のシンポジウムであり、感染症治療薬の安全性の向上を推進する。
オーガナイザー 岡田 賢二 横浜薬科大学 臨床薬剤学研究室 座長 岡田 賢二 横浜薬科大学 臨床薬剤学研究室 大石 智洋 川崎医科大学 臨床感染症学教室
SY2-1 感染症治療薬安全対策部会の活動キックオフ
岡田 賢二 横浜薬科大学 臨床薬剤学研究室
SY2-2 抗菌薬による重大の副作用の症例検討 −検査値異常からの副作用のアプローチ−
平野 公基 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 薬剤科
SY2-3 抗菌薬誘発の薬物アレルギーのアプローチと対策-臨床医の立場から-
大石 智洋 川崎医科大学 臨床感染症学
SY2-4 抗微生物薬の供給不足に対応した適切な代替薬の選択
上田 真也 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 薬剤部
シンポジウム3
8月2日(土)13:30~15:30 第1会場
ちょっと先の未来地図 -デジタルとAIが拓く薬剤師業務の新知識と挑戦-
デジタル技術は想像を超えた速さで進歩し、AIは私たちが恩恵を受けていると認知していないだけで多くのところで実走され生活の一部になっている。医療においても多くのIT業界の方が変革に取組んでおり、薬剤師は医薬品情報のアップデートと同じくらいデジタルツールのアップデートが必要となっている。今回はAIやデジタル技術の活用がもたらす少し先の未来における薬剤師に必要な知識と挑戦すべき事について、参加者と共に考えたい。
オーガナイザー 高畠 啓輔 河北総合病院 座長 桂 英之 国民健康保険 小松市民病院 薬剤科 平川 大輔 札幌心臓血管クリニック 薬剤科
SY3-1 医療DXとAIが創る医療・薬学の現在と未来
桐生 嘉浩 株式会社 メディカスタッフプロモーション 医療情報/医薬品情報システム開発室
SY3-2 副作用データベース解析におけるAI技術の活用
植沢 芳広 明治薬科大学 医療分子解析学研究室
SY3-3 保険薬局におけるDX推進について
長谷川 佳孝 株式会社アインホールディングス 医療連携学術部
SY3-4 病院でのデジタルやAIの活用体験
岩西 雄大 医療法人嘉健会 思温病院 薬剤科
シンポジウム4
8月2日(土)13:30~15:30 第2会場
各種診療ガイドラインを周産期薬物治療に活かす
周産期における薬物治療の実践に際しては、医薬品添付文書のみならず、多くの情報源を確認する必要がある。その中でも、各種診療ガイドラインにおける記載は、原疾患の治療・管理を念頭に、専門家らによって周産期管理が検討された上で記載されている。そこで、本シンポジウムにおいては、各種診療ガイドラインにおける周産期薬物治療に関する記載の現状を理解・考察し、実際の周産期薬物治療において、医薬品の安全性という観点で、各種診療ガイドラインをどのように活かしていくべきかについて議論したい。
オーガナイザー 小原 拓 東北大学病院薬剤部 座長 鈴木 俊治 日本医科大学 産婦人科 薄井 健介 東北医科薬科大学薬学部 病院薬剤学教室
SY4-1 各種診療ガイドラインにおける周産期薬物治療の記載
小原 拓 東北大学病院 薬剤部
SY4-2 産婦人科診療ガイドラインを周産期薬物治療に活かす
鈴木 俊治 日本医科大学 産婦人科
SY4-3 「こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般向け)」を周産期薬物治療に活かす
鈴木 映二 東北医科薬科大学医学部 精神科学教室
SY4-4 小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(改訂第2版)を周産期薬物治療に活かす
土屋 雅美 慶應義塾大学 薬学部 医薬品情報学講座
SY4-5 生物学的製剤を使用するような疾患の診療ガイドライン等を周産期薬物治療に活かす
土屋 貴 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 薬剤部
シンポジウム5
8月2日(土)16:50~18:50 第1会場
医療DX時代到来!! 医薬品安全にデジタル技術をどう活用していくか?
医療業界全体ではデジタル化の普及は遅れていたが、近年のコロナ禍においてオンライン診療や服薬指導、カンファレンスなどが急速に進展し、医療DXが国の主導で加速している。特に国ではオンライン資格確認を基盤とした情報共有が稼働し、保険薬局では患者の薬剤情報へのアクセスが向上し業務効率化が期待されている。このような状況下において医薬品の安全性といった観点からもさまざまなデジタルツールの活用が期待される。本シンポジウムでは電子処方箋をはじめ、様々なデジタルツールを活用した医薬品安全への取り組みについて紹介するとともに、現状における問題点、今後の展望についても広く議論する機会としたい。
オーガナイザー 荒川 隆之 長久堂野村病院 薬剤科 座長 瀧 祐介 菊川市立総合病院 薬剤科 荒川 隆之 長久堂野村病院 薬剤科
SY5-1 薬局薬剤師視点での医療DXツールの開発と社会実装-腎排泄型薬剤処方監査支援システムを中心に-
近藤 悠希 熊本大学 大学院生命科学研究部 薬物治療設計学分野(臨床薬理学)
SY5-2 医薬品安全のための情報の蓄積と共有 ―デジタルプラットフォームAI-PHARMAの活用―
神崎 浩孝 木村情報技術株式会社 イノベーション本部
SY5-3 医薬品安全の視点から電子処方箋の活用を考える
荒川 隆之 長久堂野村病院 薬剤科
SY5-4 医療DX時代の外来連携における薬剤師の役割とリフィル処方箋の可能性
渡邉 学 社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 医療技術部
SY5-5 オンライン服薬指導サービスにおける医薬品安全性 ―Amazonファーマシーの取り組み―
筒井 剛 アマゾンジャパン合同会社 消費財事業本部
シンポジウム6
8月3日(日)9:30~11:00 第1会場
探索から検証へ ~副作用データベースにおける実践的アプローチ~
近年、副作用データベース研究は医薬品の安全性評価において急速に注目され、数多くの仮説生成研究が実施されています。しかしながら、これらの研究は生成された仮説の検証が十分に進んでいない現状があります。副作用データベース研究において仮説検証的研究は発展途上であり、検証手法や評価基準の確立が求められています。本シンポジウムでは、探索的研究の成果と課題を共有し、検証的研究の重要性と実践的な方法を学ぶことで、データベース研究全体の信頼性向上と医薬品安全性評価の確立に寄与することを目的とします。
オーガナイザー 菅 裕亮 (株)なの花北海道 なの花薬局若草店 座長 濃沼 政美 帝京平成大学 薬学部 医薬品安全性評価学ユニット 菅 裕亮 (株)なの花北海道 なの花薬局若草店/(株)メディカルシステムネットワーク 学術部
SY6-1 副作用データベース研究のこれから:探索から検証へ
濃沼 政美 帝京平成大学 薬学部
SY6-2 臨床現場からはじまる副作用データベース解析
菅 裕亮 (株)なの花北海道 なの花薬局若草店/(株)メディカルシステムネットワーク 学術部
SY6-3 仮説生成のその先へ:リアルワールドデータを活用した仮説検証に基づく医薬品安全性評価
岡田 直人 山口大学 医学部附属病院 薬剤部
SY6-4 医療情報を用いた副作用・薬効予測とその臨床応用
濱野 裕章 岡山大学学術研究院 医療開発領域 薬剤部
シンポジウム7
8月3日(日)9:30~11:00 第2会場
研究者と現場薬剤師のI 型・T型・H型人材が協働するとどうなる? ~帯状疱疹治療薬の安全性を極める!
I型人材とは、専門性に特化したスペシャリスト的な人材で、研究者が該当するとされる。そして、T型・H型人材は強い専門性を誇る分野が1つあり、広く他の分野に知見を持つ人材(T型)、他人の専門性を横軸で繋げられる架け橋となる人材(H型)を指す。今回、化学・病態・薬物動態各領域におけるI型・T型人材の専門性を、医薬品副作用情報部会メンバーがH型人材として臨床につなぐ架け橋となり、帯状疱疹治療薬の安全性を極める個別最適化を目指した。 その成果(イノベーション)について紹介すると共に、基礎薬学を活用した使い分けにより、帯状疱疹治療薬の安全性をいかに極めるかについて考えてみたい。
オーガナイザー 杉山 奈津子 国際医療福祉大学薬学部
小茂田 昌代 医療法人徳洲会千葉西総合病院薬剤部
岸 達生 公益財団法人 日本薬剤師研修センター
座長 出雲 貴文 医療法人徳洲会 千葉西総合病院 薬剤部
岸 達生 公益財団法人 日本薬剤師研修センター
SY7-1 構造式から考える帯状疱疹治療薬の化合物特性
頓宮 美樹 株式会社la vita
SY7-2 薬物相互作用を予測する~基礎の知識を臨床につなげる
宗像 千恵 国際医療福祉大学 福岡薬学部 薬学科
SY7-3 知ってますか?脳症と脳炎の違い!
小茂田 昌代 医療法人徳洲会 千葉西総合病院 薬剤部
SY7-4 基礎薬学的特性を臨床で活用する(協働作成資料の紹介とその活用)
長澤 宏之 セコム医療システム株式会社 運営監理部
SY7-5 「帯状疱疹治療アカデミック・ディテーリングによる患者リスク低減プログラム」の実践
杉山 奈津子 国際医療福祉大学 薬学部 薬学科
シンポジウム8
8月3日(日)13:20~15:20 第1会場
認知症薬物治療のアップデート −薬物治療の適正化を思考して−
認知症の薬物治療環境は、コリンエステラーゼ阻害薬の3剤とNMDA受容体拮抗薬1剤が発売されてから13年間大きな変化がなく停滞していました。しかし、2023年にレケンビ(R)点滴静注、2024年にケサンラ(R)点滴静注液がモノクローナル抗体制剤として発売され、2023年にドネペジルの貼付製剤であるアリドネ(R)パッチが発売、2024年にはレキサルティ(R)に認知症BPSDの適用が追加されて、薬物治療環境に賑わいがみられています。さらに2025年には地域包括ケアシステムが完成して、今、認知症への対応が大きく変わろうとしています。この変化に薬剤師がどのように対峙するのかを医療安全の面から考えたいと思います。
オーガナイザー 薄井 健介 東北医科薬科大学薬学部病院薬剤学
三輪 高市 鈴鹿医療科学大学大学院薬学研究科
座長 山田 和男 東北医科薬科大学・医学部
三輪 高市 鈴鹿医療科学大学大学院・薬学部 薬学研究科・薬学科
SY8-1 認知症薬物療法の近況
三輪 高市 鈴鹿医療科学大学大学院・薬学部 薬学研究科・薬学科
SY8-2 モノクローナル抗体製剤の使用状況と注意すべきポイント
別所 千枝 JA広島厚生連 尾道総合病院 薬剤科
SY8-3 認知症治療における貼付剤の意義と安全性
和田 智仁 社会医療法人居仁会 総合心療センターひなが 診療技術部薬剤課
SY8-4 認知症患者の“行動”にどう向き合うか―BPSDの薬物療法とそのリスクマネジメント
中村 友喜 三重県立こころの医療センター 診療技術部/感染管理室
シンポジウム9
8月3日(日)13:20~15:20 第2会場
一つ一つの薬を評価する、それが私たちの使命です! ~ポリファーマシー解消の第一歩~
ポリファーマシーの解消には、多職種連携、地域連携などが必須であるが、その第一歩は薬剤師が薬剤と患者を総合的に評価し、薬の必要性を評価することである。しかし、急性期病院においては患者の在院日数が短く、保険薬局では患者面談の時間は限られている。限られた時間の中で効率よく評価するためには、ツールを活用し効率的に行うことが求められる。一方で、ツールはあくまで補助的なものであり、薬学的視点に基づいた薬剤師による患者の個別評価が不可欠である。本シンポジウムでは、ツールの活用事例や課題を共有し、どのように一つ一つの薬を評価し、ポリファーマシー解消を進めていくかを議論したい。
オーガナイザー 廣田 憲威 一般社団法人大阪ファルマプラン 座長 山﨑 美保 独立行政法人 労働者健康安全機構 長崎労災病院 薬剤部 神原 弘恵 尾道市立市民病院 薬剤部
SY9-1 薬局の限られた情報から処方内容を評価する
杉本 陵 ウエルシア薬局
SY9-2 Deprescribing実践プロトコルに基づく薬剤師の介入が有用であった一症例
柳下 博信 秋田大学医学部附属病院 薬剤部
SY9-3 薬学的視点×モダリティ×身体所見で副作用を評価し薬物療法の適正化
佐古 守人 医療法人橘会 東住吉森本病院 薬剤部 臨床薬剤科
SY9-4 ポリファーマシー対策の第一歩 ~患者の暮らしに寄り添う薬物療法の見直し~
武藤 浩司 新潟市民病院 薬剤部
教育講演1
薬物と性差
8月2日(土)13:30~14:30 第3会場
座長 佐藤 由美子 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 薬剤部
演者 黒川 洵子 静岡県立大学 薬学部 生体情報薬理学分野
教育講演2
生体における亜鉛の重要性 〜疾患の発症との関連・治療/予防への応用〜
8月2日(土)14:30~15:30 第3会場
座長 佐藤 光利 明治薬科大学 医薬品安全性学教室
演者 西田 圭吾 鈴鹿医療科学大学薬学部 免疫制御学研究室
教育講演3
有害事象自発報告ビッグデータを用いた医薬品適正使用に係る研究
8月2日(土)16:50~17:50 第2会場
座長 髙栁 和伸 倉敷中央病院 薬剤本部
演者 中村 光浩 岐阜薬科大学 医薬品情報学研究室
教育講演4
薬剤師に期待する:Pharmacist/Scientistの視点を持つ
8月3日(日)9:00~10:00 第3会場
座長 山田 成樹 藤田医科大学医学部薬物治療情報学講座 / 藤田医科大学病院 薬剤部
演者 鍋島 俊隆 特定非営利活動法人 医薬品適正使用推進機構
教育講演5
医薬品の安全性データを読み解く −臨床試験、疫学研究、そして実臨床でできること−
8月3日(日)10:00~11:00 第3会場
座長 古関 竹直 藤田医科大学医療科学部 研究推進ユニット レギュラトリーサイエンス分野
演者 中林 哲夫 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部
BP賞候補演題
8月2日(土)10:40~12:04 第1会場
座長 牧田 亮 岐阜県総合医療センター 薬剤部 小林 亮 岐阜薬科大学 先端医療薬学研究室
BP-1 クロザピンによる抗精神病薬多剤併用と痙攣発症:FDA有害事象自発報告システムを用いた安全性シグナル評価
吉原 希(藤田医科大学 医学部 薬物治療情報学講座)
BP-2 小児炎症性疾患におけるメトトレキサートの肝機能障害リスク: リアルワールドデータを用いた自己対照研究
中國 正祥(国立成育医療研究センター 臨床研究センター)
BP-3 高濃度カリウム製剤による医療事故防止を目指した輸液中40K定量法の開発
栄井 修平(兵庫医科大学薬学部)
BP-4 データ抽出ツールを活用した生理学的薬物速度論モデル解析
吉年 勉(兵庫医科大学大学院 薬学研究科)
BP-5 JADERを用いた抗生剤による薬物性肝障害に対するウルソデオキシコール酸投与の発症予防効果を検討
追川 俊哉(東京ベイ・浦安市川医療センター 薬剤室)
BP-6 薬剤師による造影剤副作用情報の管理体制の整備
荒木 良介(大和市立病院 薬剤科)
BP-7 漢方薬とインテグラーゼ阻害薬の吸収過程における薬物相互作用の可能性;多価金属含有量を加味した検討
山内 萌子(東邦大学 薬学部 実践医療薬学研究室)
一般演題1
その他①
8月2日(土)10:10~10:58 第4会場
座長 山﨑 直子 駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 薬剤科 渡邉 学 駿甲会法人本部 / コミュニティーホスピタル甲賀病院 医療技術部
O1-1 ワクチン調製の安全性向上を目指した薬局・病院薬剤師の連携ー筑紫医療圏の新型コロナワクチン接種対応から
宮﨑 元康(福岡大学 薬学部 病院薬学教室)
O1-2 実務実習日誌への入力医薬品と薬剤師国家試験の出題医薬品の対応から薬学生に求められる医薬品安全性の検討
木下 雅子(東邦大学 薬学部 臨床薬剤学研究室)
O1-3 安全で円滑な医療提供体制の構築を目指した院内処方における疑義照会プロトコル導入の効果と今後の課題
吹上 勇真(福岡大学筑紫病院)
O1-4 薬局における地域医療情報連携ネットワーク活用実態調査
相宮 幸典(藤田医科大学 医学部 薬物治療情報学講座)
一般演題2
症例検討(有害事例、回避事例、等)
8月2日(土)10:58~12:10 第4会場
座長 藤谷 憲一 リラ溝口病院 薬局 瀧 祐介 菊川市立総合病院 薬剤科
O2-1 HiSATを用いて特定したフェニトインによる薬疹の1例
安高 勇気(福岡大学 薬学部)
O2-2 易怒性に対するクロルプロマジン使用中に重度肝機能障害を来した症状性精神障害の一例
中村 怜(東北医科薬科大学 医学部 精神科学教室)
O2-3 新規抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤の継続が困難だった1例
萩原 知佳(福岡大学筑紫病院 薬剤部)
O2-4 副作用推論~この血小板減少は薬のせいですか?~
鈴木 孝司(公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院)
O2-5 レンバチニブによって血栓性微小血管障害を発症した1例
舟橋 季乃(名城大学 薬学部 医薬品情報学研究室)
O2-6 オピオイド鎮痛薬の変更により疼痛コントロール可能となった一例
澁谷 恵美子(IHI播磨病院)
一般演題3
安全対策・管理(薬局、調剤・注射、製剤、病棟、外来、等)
8月2日(土)13:30~14:30 第4会場
座長 安田 浩二 岐阜大学医学部附属病院 薬剤部 西田 承平 岐阜大学医学部附属病院 薬剤部
O3-1 麻薬滅失事故の発生原因分類と再発防止対策の効果についての調査
冨岡 謙二(山陰労災病院)
O3-2 外来化学療法における薬剤師介入の実態とその有用性及び安全性の検討
福江 悠香(福岡大学筑紫病院 薬剤部)
O3-3 病院薬剤師業務に伴うインシデント発生状況と背景因子
宇井 あゆ乃(東邦大学 薬学部 実践医療薬学研究室)
O3-4 リハビリテーション病院における薬剤使用の実態と転倒・転落に関する後ろ向き研究
齊藤 優海(東邦大学 薬学部 実践医療薬学研究室)
O3-5 大阪ファルマプラン副作用委員会2023-2024のまとめ
岩本 咲央里(大阪ファルマプラン すみれ薬局)
一般演題4
薬剤疫学、副作用、使用状況調査、データベース研究、ベネフィット・リスク評価研究①
8月2日(土)14:30~15:18 第4会場
座長 木村 謙吾 市立四日市病院 薬局 奥平 正美 知多厚生病院 薬剤部兼感染制御部
O4-1 医薬品副作用データベースを用いたアルテプラーゼ誘発頭蓋内出血に及ぼす抗凝固薬/抗血小板薬の影響の解析
中井 剛(藤田医科大学 医学部 薬物治療情報学)
O4-2 抗精神病薬と心筋梗塞:過去の疫学研究と最近の薬剤疫学的知見
中川 誠秀(東北医科薬科大学精神科学教室)
O4-3 VigiBaseを用いた免疫チェックポイント阻害薬による骨折シグナルの調査研究
家田 諒(藤田医科大学 医学部 薬物治療情報学)
O4-4 大阪民医連副作用委員会~2023年度報告まとめ~
福田 千佳(コープおおさか病院 薬剤科)
一般演題5
薬剤疫学、副作用、使用状況調査、データベース研究、ベネフィット・リスク評価研究②
8月2日(土)16:50~17:38 第4会場
座長 梶間 勇樹 三重ハートセンター 薬局 谷口 賢二 JA三重厚生連 松阪中央総合病院
O5-1 COVID‑19入院患者におけるモルヌピラビルの安全性評価―単施設後ろ向きコホート
山田 楊太(福岡大学筑紫病院 薬剤部)
O5-2 医薬品副作用データベース(JADER)を用いたサクビトリルバルサルタンによる脱水発現リスクの解析
折川 隼人(株式会社アインファーマシーズ アイン薬局東鷲宮店)
O5-3 医薬品副作用データベース(JADER)を用いた抗がん剤による重症皮膚副作用の発現リスク解析
花岡 美早紀((株)アインファーマシーズ アイン薬局 愛大病院店)
O5-4 医薬品副作用データベース及び診療録を用いたBMIによるEnfortumab Vedotinの副作用発現傾向調査
慶 元箕(東京女子医科大学附属足立医療センター 薬剤部)
一般演題6
その他②
8月2日(土)17:38~18:50 第4会場
座長 田宮 真一 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二赤十字病院 薬剤部 手塚 剛彦 愛知医科大学メディカルセンター 薬剤室
O6-1 佐渡総合病院における活性型ビタミンD3製剤適正使用のための取り組みとその評価
森岡 諒(佐渡総合病院 薬剤部)
O6-2 炎症性腸疾患患者の生物学的製剤の治療中止に及ぼす因子の検討
中島 章雄(福岡大学筑紫病院 薬剤部)
O6-3 電子処方箋運用に向けたローカル用法と電子処方箋用法の対応状況の調査
寺内 恭平(藤田医科大学 医学部 薬物治療情報学)
O6-4 CYP1A2関連医薬品に対する喫煙の影響を考慮することの重要性
西 桃佳(東京理科大学 薬学部 臨床病態学研究室)
O6-5 処方適正化への取り組み
上野 綾海(菊川市立総合病院 薬剤科)
O6-6 医薬品添付文書と当院電子カルテにおける牛乳成分情報の調査
佐田 光(岡山大学病院 薬剤部)
一般演題7
薬剤疫学、副作用、使用状況調査、データベース研究、ベネフィット・リスク評価研究③
8月2日(土)18:00~18:48 第3会場
座長 山中 規明 一宮市立市民病院 高橋 由加利 春日井市民病院 薬剤局 薬剤科
O7-1 JADERに登録されたOTC医薬品に関連する排尿障害の抗コリン薬リスクスケールに基づく評価
田中 博之(東邦大学 薬学部 実践医療薬学研究室)
O7-2 薬剤性ギラン・バレー症候群:日本有害事象データベース(JADER)に基づく発症時期の検討
鳥海 真也(神奈川病院 薬剤部)
O7-3 JADERを用いたワクチン接種に伴う有害事象報告の実態調査
鎌田 吉宗(東邦大学 薬学部 実践医療薬学研究室)
O7-4 有害事象自発報告データベース(JADER)を用いたβ受容体遮断薬の精神神経系有害事象の検討
山田 一尊(日本赤十字愛知医療センター名古屋第一病院 薬剤部)