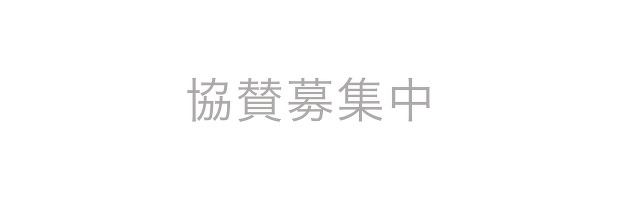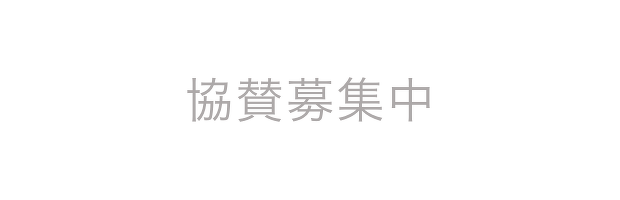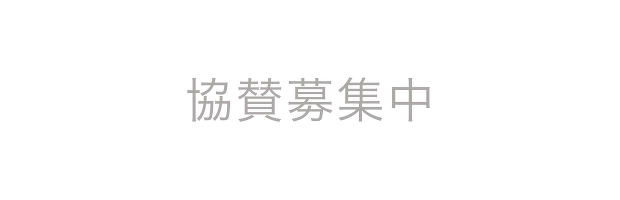大会長挨拶
この度、第27回日本在宅血液透析学会を2025年9月6日(土)・7日(日)に埼玉県川越市の川越プリンスホテルにて開催する運びとなりました。現在、スタッフ一同、鋭意準備を進めております。
当院が在宅血液透析を導入したきっかけは、透析室のスタッフからの「居宅での透析は患者さんの元気につながるのではじめませんか?」という一言でした。当時、家族と過ごす時間を大切にしたいという思いで在宅血液透析を希望された患者さんがいらっしゃり、この取り組みがスタートしました。導入当初は、医療器材の宅配や廃棄物の処理、透析用原水の供給など、多くの課題がありましたが、それ以上に患者さんの笑顔や「頑張ろう」と思える瞬間が多々あり、我々は在宅透析の質の向上に尽力していこうと決意しました。
現在、在宅血液透析は徐々に認知されつつありますが、依然として限られた患者さんにしか提供されておりません。高い生存率や生活の質(QOL)の向上が期待される一方で、家庭での治療に対する不安や拒絶感を持つ医療スタッフも多く、そのため広く普及させるための啓蒙活動と議論が不可欠です。今回の大会テーマとして、「次世代に伝ふる 〜私らしい在宅血液透析〜」と致しました。一人でも多くの患者さんやご家族が自分らしい生活を営める在宅血液透析を見つけ、それらが多くの患者さんに提供できるようになり、在宅血液透析自体が腎代替療法の一つとして重要な位置づけで未来に継承されていくような形を目指しています。これらの実現に向けて本大会では、より多くの医療機関での実践できるような知見と議論を深める場にしたいと考えております。
腎代替療法全体をより良いものにすることが最も重要だと考えています。そのためには、腎代替療法を社会により分かりやすく説明できることが大切です。透析を必要とする患者さんに対して、治療の不安を払拭し、より分かりやすく説明することで、治療への不安感を軽減し、透析を行いながらも前向きな目標を持って頑張っていただくことができます。これにより、社会への貢献にもつながり、より明るい社会を築くことができると考えています。腎代替療法には血液透析、腹膜透析、移植がありますが、患者さんの生活を中心に据え、施設透析、在宅透析、移植と言われるように、医療機関や介護施設などの専門知識を活かして腎代替療法を充実させることが重要だと考えています。そのためにも、腎代替療法の説明から実際の導入後の生活に至るまで、様々な観点から取り組みを考察し、在宅血液透析の意味を十分に理解し、その他の腎代替療法との密接な連携関係を明確にする学会を目指しています。また、腎不全合併症に対応することも重要です。在宅医療と合併症の対策についても、バスキュラーアクセスをはじめとする血管合併症やCKD-MBD、糖尿病関連など様々な問題に対処する必要があります。これらの課題について、参加者が有意義に学習できるよう、最大限の配慮をしたいと考えています。
9月初めのまだ暑い時期ではありますが、埼玉川越は小江戸と呼ばれる城下町であり、会場から徒歩圏内で情緒豊かな街並みをお楽しみいただけると幸いです。皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。
第27回日本在宅血液透析学会
大会長 小川智也
埼玉医科大学総合医療センター
腎・高血圧内科 教授/血液浄化センター長